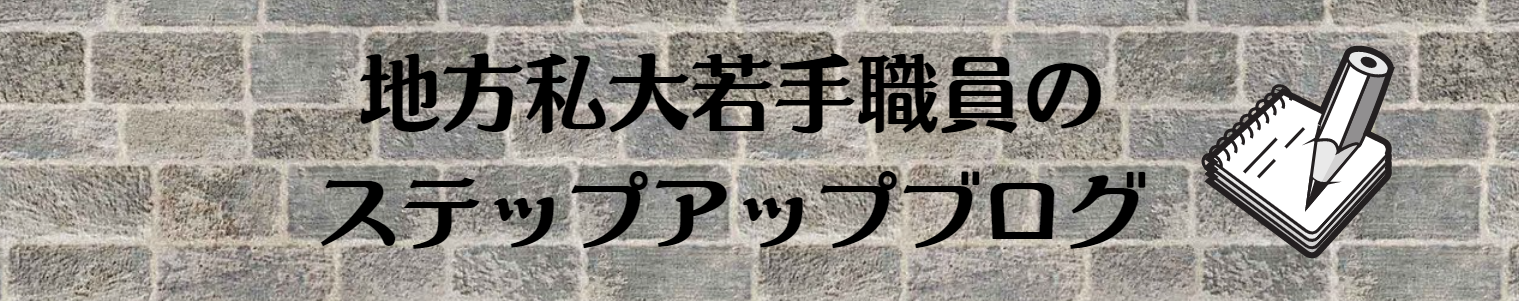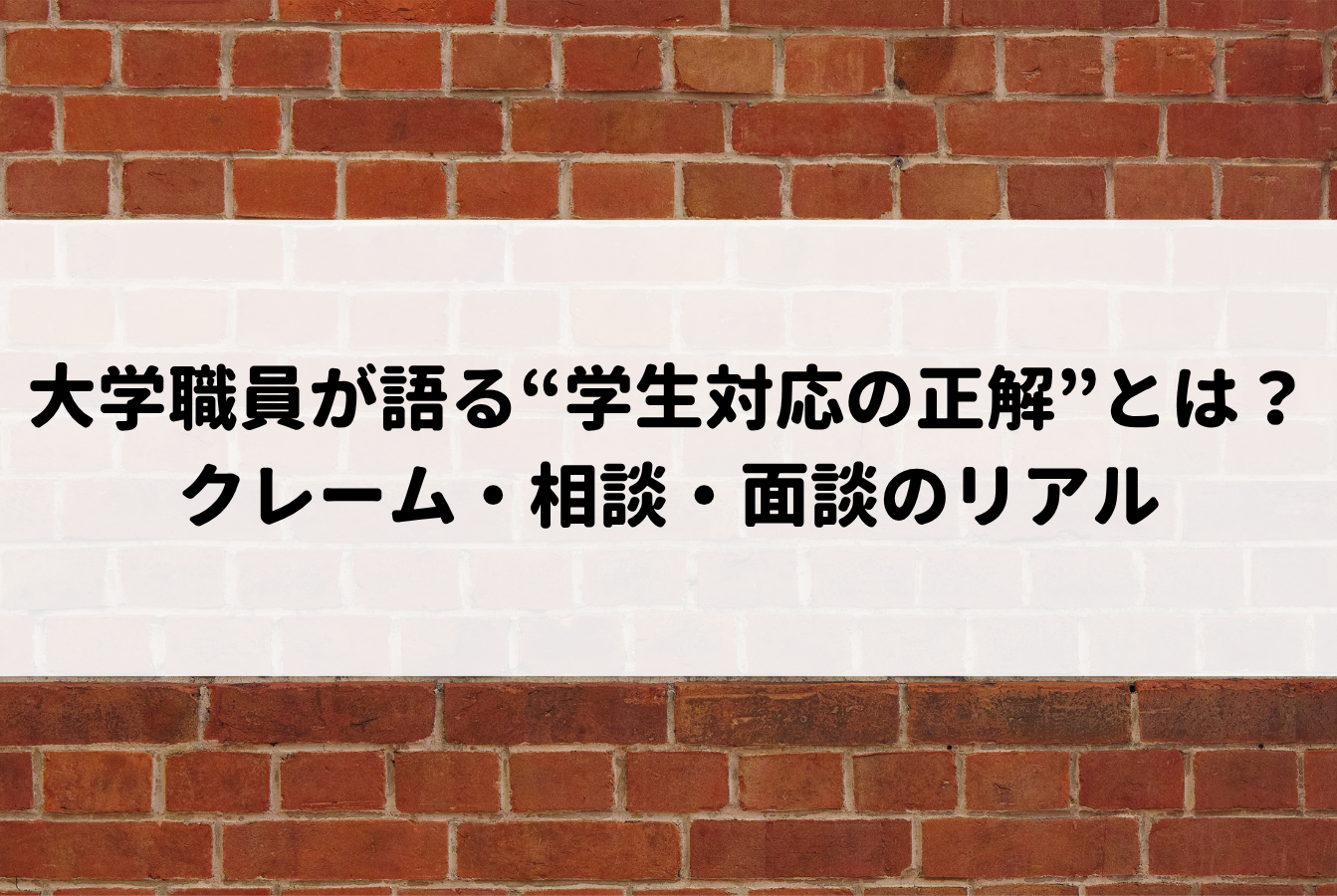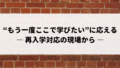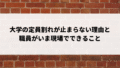こんにちは、ここあです!
大学の事務室にいると、日々さまざまな学生が訪れます。履修や生活トラブルの相談、拾得物の確認、そしてときには感情的なクレームまで――。
そんな時、職員として「どんな対応が正解なのか」と悩む瞬間は少なくありません。
この記事では、大学職員として多くの学生と向き合ってきた立場から、現場で実感する“学生対応のリアル”を紹介します。決してマニュアルではカバーしきれない、実際のやり取りや姿勢を中心にまとめました。
「正論よりも、まず受け止める」――学生対応の第一歩
学生対応で最も大切なのは、正論をすぐにぶつけないことです。
たとえば、提出期限を過ぎた書類を持ってきた学生に対して、「期限は過ぎています」と伝えるのは当然ですが、それだけでは相手は納得しません。
「どうして遅れたのか」
「今どんな状況なのか」
まずはこの2点を丁寧に聞き取ることが重要です。
背景を知れば、学生の中には家庭の事情や精神的な不調など、本人の努力ではどうにもならない事情を抱えていることもあります。
“受け止めてから伝える”という順序が、結果的に学生の信頼を得る近道になります。
クレーム対応の基本は「冷静な翻訳力」
クレームや強い言葉での訴えは、大学現場でも少なくありません。
「担当教員の態度がひどい」「説明が不十分だ」「自分だけ不利に扱われた」など、学生・保護者の感情が前面に出るケースもあります。
そんな時に意識したいのが、「翻訳して受け取る力」です。
相手の言葉をそのまま感情として受け止めるのではなく、
「つまりどうしてほしいのか」「何に不安を感じているのか」を言語化して整理するのです。
怒りの裏には、不安や孤独が隠れていることが多いもの。
感情を落ち着けてから事実関係を確認し、大学としての対応方針を共有すると、自然とトーンが和らぎます。
クレームは“火消し”ではなく、“信頼回復”の機会だと捉えると、見える景色が変わります。
面談対応で意識したい「沈黙の活用」
学生との面談では、つい質問を重ねすぎたり、アドバイスを早く出そうとしたりしてしまいがちです。しかし実際には、沈黙の時間こそが学生の本音を引き出すチャンスです。
沈黙に耐えきれずに職員が話してしまうと、学生は「話を聞いてもらえない」と感じることがあります。あえて数秒の沈黙を置き、「焦らず話して大丈夫だよ」という空気をつくることが、信頼関係を深めます。

「面談=話す場ではなく、”考えを整理する場”として支援する。」
この意識があるだけで、学生の表情や反応は明らかに変わります!
「正解」を求めすぎない――現場での割り切りも必要
学生対応をしていると、「どう答えるのが正解だったのか」と悩むことが多々あります。
しかし、教育現場に“唯一の正解”は存在しません。
学生ごとに背景も、価値観も、ゴールも違うからです。
職員ができるのは、その瞬間にできる最善を尽くすこと。
「この対応で良かったのか」と迷う気持ちは、裏を返せば“真剣に向き合った証”です。
完璧を目指すよりも、「また次に活かせばいい」と前を向く姿勢が、長くこの仕事を続ける上での支えになります。
おわりに
学生対応は、感情労働とも言われるほど神経を使う仕事です。
それでも、面談後に学生が「少し楽になりました」と言ってくれる瞬間は、何にも代えがたいものがあります。
大学職員という仕事は、“ルールに沿って処理する仕事”ではなく、“相手を想い行動する仕事”です。
時に難しい判断を迫られながらも、学生の成長を見届ける――
その積み重ねこそが、大学職員としての誇りではないでしょうか。
以上、お読みいただきありがとうございました!