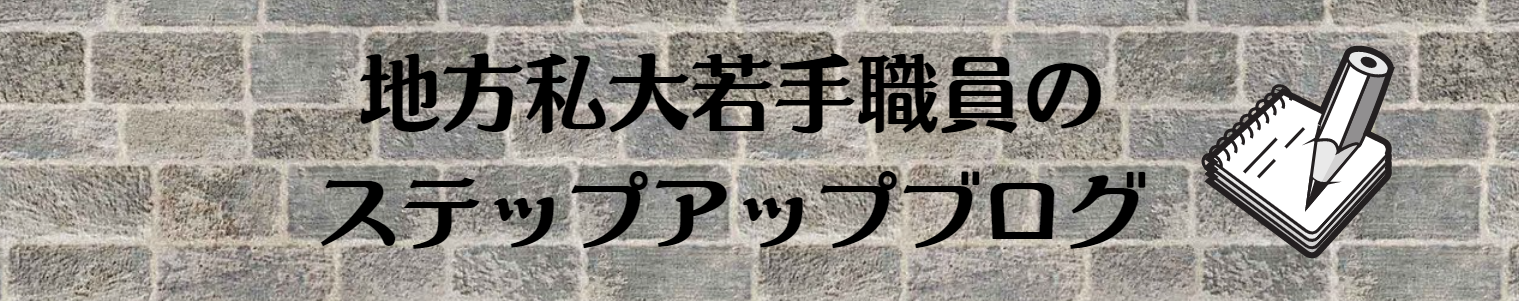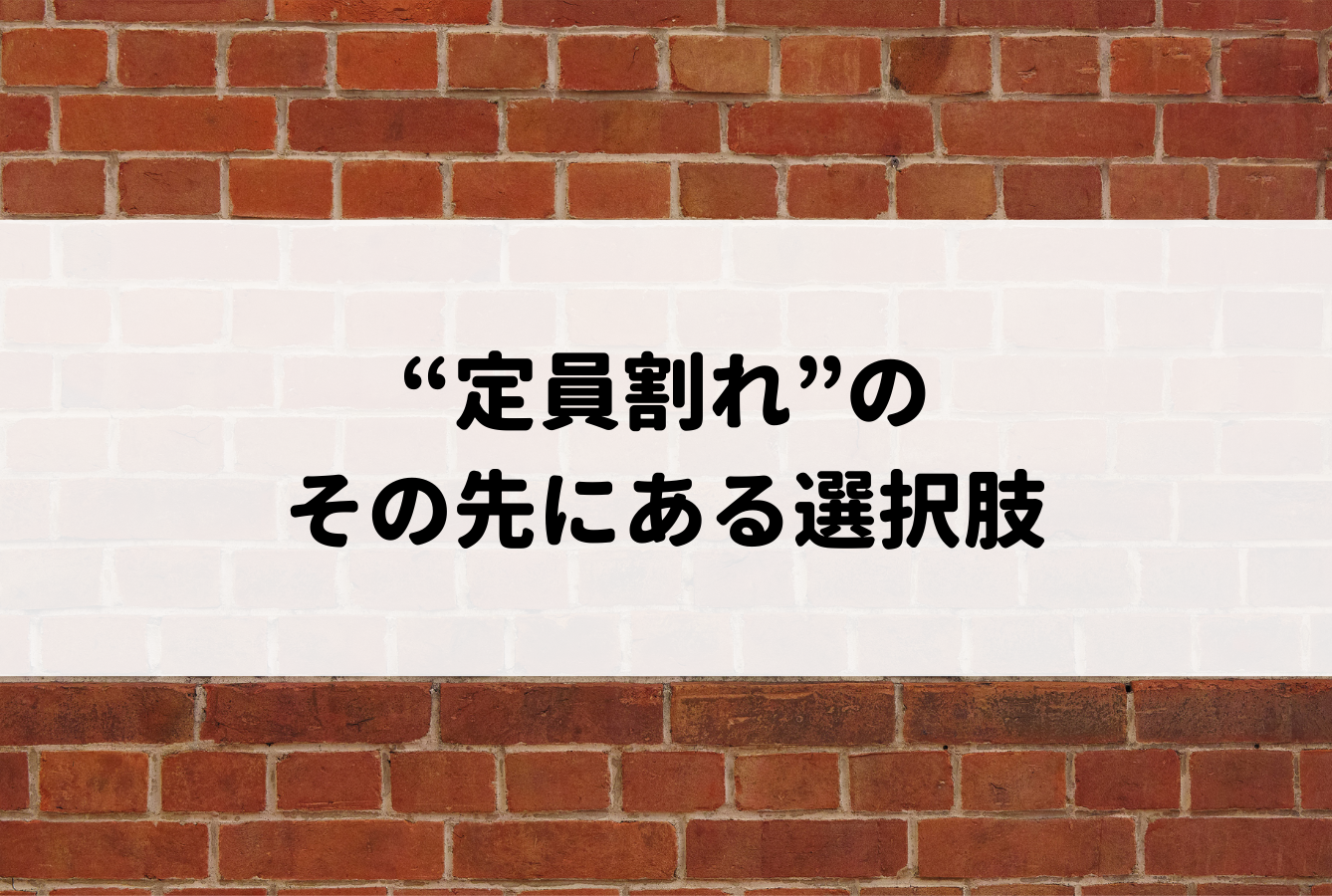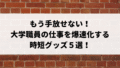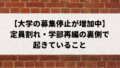こんにちは、ここあです。
最近、「大学の定員割れ」という言葉を耳にする機会が増えてきました。新聞や進学サイトの記事では、志願者数の減少や、地方大学を取り巻く厳しい状況が取り上げられています。
私が勤務している大学は、幸いなことに現時点においては比較的安定して入学定員を確保できているようで、直接的に“定員割れ”という言葉を突きつけられている状況にはありません。しかし、大学の現場で働く者としては「このままでいいのだろうか?」と考える瞬間は多々あります。
定員割れが他人事では済まない時代がもう目の前に来ている。そう感じるからです。
定員割れとは何か──数字の奥にある意味
「定員割れ」とは、一般的に大学の入学者数が募集定員を下回る状態を指します。経営面での打撃はもちろん、大学全体の活力や学生の学びにも影響を及ぼす重大なテーマです。
でも実は、“数字上は割れていなくても”大学が抱える課題はじわじわと進行しているケースも少なくありません。たとえば、進学動機があいまいなまま入学してくる学生、学びに対するモチベーションが低いまま日々を過ごす学生…。こうした傾向が見られる大学は、表面上の定員が満たされていても、長い目で見たときに将来的な“割れ”につながる可能性もあるのです。
志願者減少が示すサイン
全国的に見ると、志願者数が少しずつ減り続けているのは事実です。特に、18歳人口の減少に加え、都心志向の高まり、専門学校や就職という多様な選択肢の広がりも影響しています。
地方の大学では、もはや「入学者を集める」だけでなく、「この大学を選ぶ理由をいかに提供できるか」が問われる時代になってきています。言い換えれば、“選ばれる大学”であり続けるための工夫と努力が、以前にも増して必要になっているということです。
客観的に見えてくる、大学職員の役割
私自身は学生支援など、大学生と直に接する機会がある業務に携わっています。そのなかで感じるのは、数字以上に、学生の言葉や表情に未来の兆しがあるということです。前向きな大学生活を送ってくれている学生がいる一方で、大学への諦めに近い感情を抱きながら生活している学生も複数存在します。
そう考えると、日々の学生対応一つひとつを大切にしなけければと、改めて考えさせられます。私たち職員にできることは決して派手なことばかりではありませんが、大学の魅力をきちんと“見える化”し、正しく届けていくことは、まさに今後ますます重要になるのだろうと思います。
今、できる備えとは
今はまだ安定していても、今後もずっとこの状態が続くとは限りません。では、どんな備えができるのでしょうか。
たとえば…
- 学生からの声を積極的に拾い、大学運営に反映させる仕組み
- 在学生の成功体験を発信し、“リアルな魅力”を届ける広報
- 高校や地域と連携した、新たな学びの形の模索
どれも小さなことかもしれませんが、これらの積み重ねが「この大学を選んでよかった」と思ってもらえるきっかけになります。
おわりに
定員割れという状況がすぐに我が身にふりかかるわけではない。これは私自身大変ありがたいことだと感じています。しかし、だからこそ今、冷静に、客観的に、この問題を見つめる必要があるとも言えます。
志願者数が減りゆく時代に、大学の存在意義が問われています。その中で、職員一人ひとりができることはきっとあるはずです。
“まだ大丈夫”ではなく、“今だからこそ考えておきたい”。未来の変化に備えるために、今できる一歩を踏み出していきましょう!
以上、お読みいただきありがとうございました!