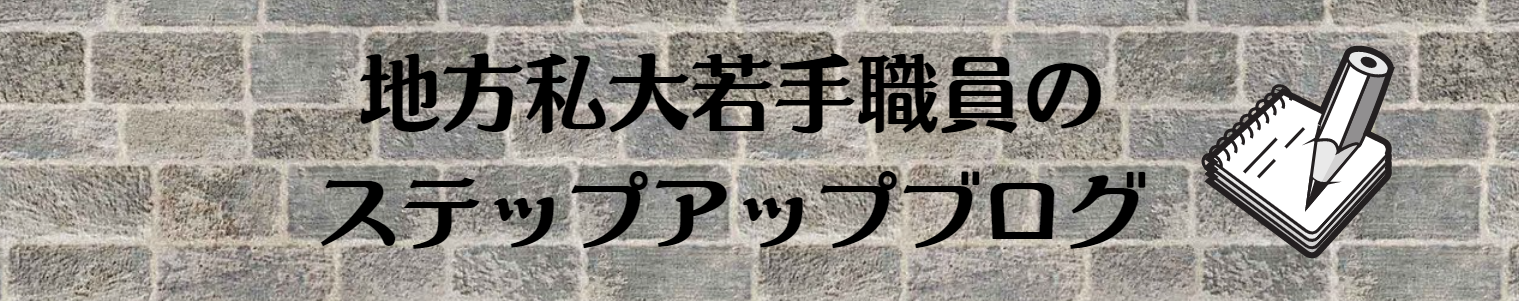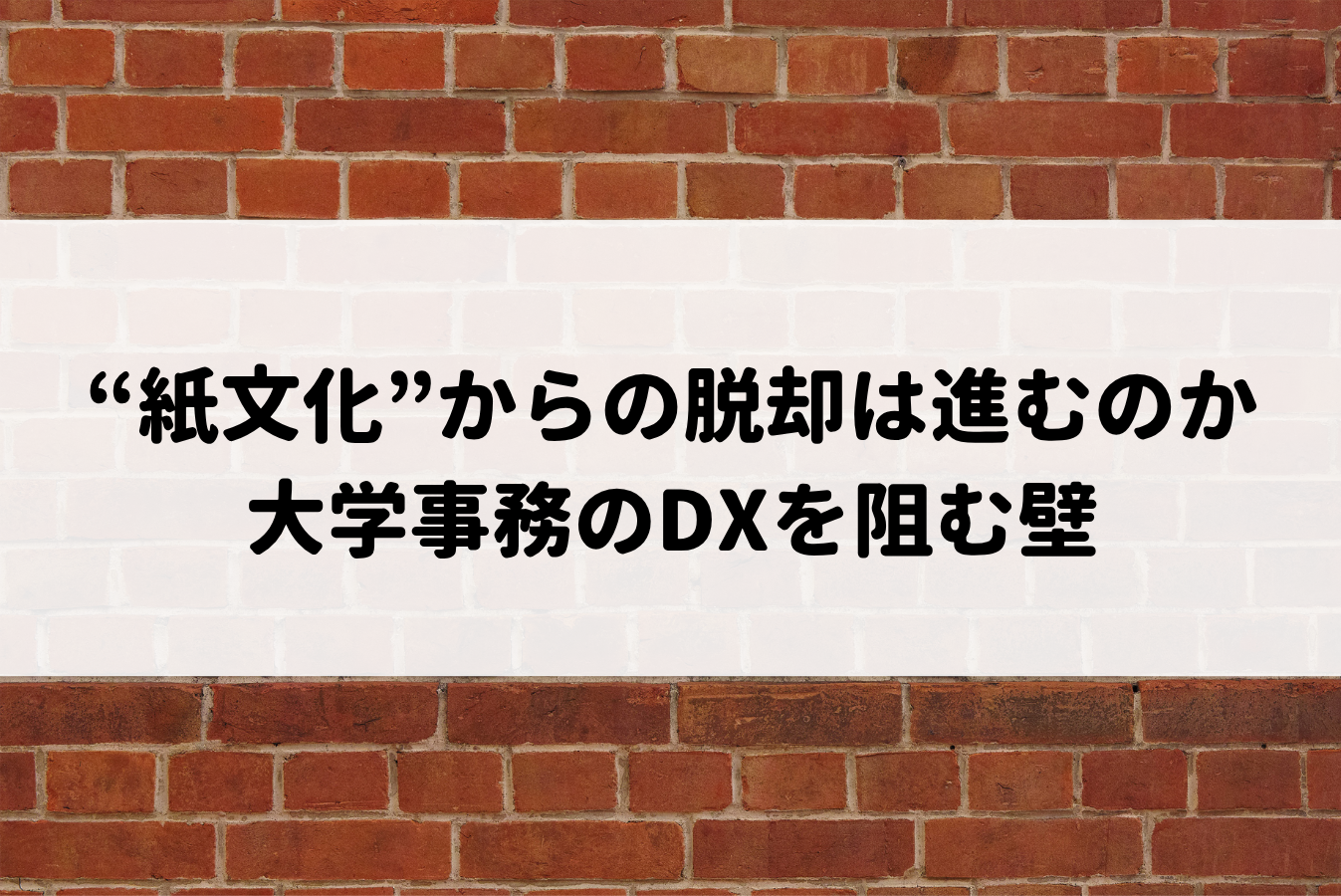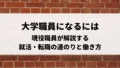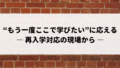学生はオンラインで履修登録を済ませ、スマートフォンひとつで成績や休講情報を確認します。
それでも、大学職員のデスクには今なお“紙の山”が積み上がっている――そんな光景は珍しくありません。
また、奨学金の申請書、部活動の届出、会議の資料、そして押印を求める稟議書など、どれも業務の効率化を目的に電子化が検討されてきたものばかりですが、実際の現場では「結局紙の方が早い」という声があることも事実です。
“DX(デジタルトランスフォーメーション)”という言葉が定着して久しい今でも、大学事務においては、その波が完全に届いているとは言いがたい状況です。
では、なぜ大学の「紙文化」はこれほどまでに根強く残っているのでしょうか。
そこには、単なる技術やシステムの問題を超えた、“文化としての慣習”が深く関係しています。
1.決裁・押印文化の根強さ
大学に限らず、公的機関では「書面による決裁」や「押印」が長年の慣習として根づいています。
特に大学は、学内規程や稟議の仕組みが紙ベースを前提に作られているため、電子承認に切り替えるには制度面の見直しが必要です。
さらに、書類に印鑑を押すという行為には、「確認した」「責任を持つ」という心理的な安心感が伴います。
そのため、電子決裁に対して「本当にこれで大丈夫なのか」「後から証拠が残るのか」といった不安を感じる職員も少なくありません。
こうした“紙=安心”という感覚が、デジタル化を進める上での最初の壁になっています。
実際、電子承認システムを導入しても、最終的には紙で印刷して保管するという“二重運用”が行われているケースも見られます。
2.現場職員の“便利さ”への不安
もうひとつの大きな壁は、現場の職員が感じる「紙の方が便利」という実感です。
紙ならすぐに見返せて、メモを書き込むこともできる。
新しいシステムが導入されても、操作に慣れるまでは時間がかかり、結局“紙に戻る”ということもあります。
また、電子化によってかえって作業が増えるケースもあります。
例えば、届出を紙で受け取った後に、同じ内容をシステムへ入力する――。
これでは「DX」というより、むしろ“手間の上乗せ”です。
DXの目的は業務の効率化であるはずが、「新しい仕組みが増えたせいで、仕事が複雑になった」と感じる職員が出てくると、現場のモチベーションは下がってしまいます。
こうした小さな不満が積み重なり、デジタル化への抵抗感を生むことも少なくありません。
3.システム導入と運用のミスマッチ
もうひとつ見過ごせないのが、システム導入と実際の運用とのずれです。
多くの大学では、専門のシステム担当者が限られており、開発や運用を外部業者に任せるケースが多く見られます。
しかし、現場の業務を十分に理解しないまま設計されると、実際の運用に合わないシステムになってしまうことがあります。
その結果、「便利なはずなのに使いづらい」「結局紙で確認した方が早い」という声が上がるのです。
さらに、導入後のサポート体制が十分でない場合、トラブルが起きてもすぐに対応できず、結局「紙運用に戻すしかない」という判断に至ることもあります。
こうした経験が重なると、職員の間に「どうせうまくいかない」というあきらめの空気が広がり、DXへの期待が薄れてしまいます。
4.それでも、変化は始まっている
それでも、少しずつではありますが、変化の兆しも見えています。
オンラインでの稟議やクラウド申請、電子契約などを導入する大学も増えてきました。
これらの取り組みは、単なるシステム導入にとどまらず、「業務の流れそのものを見直す」という視点で進められています。
特に成功している大学に共通しているのは、「現場の声を取り入れながら設計している」という点です。
便利さだけを追い求めるのではなく、「現場が無理なく使える仕組み」を大切にしているのです。
その背景には、「DXはシステムではなく文化の変革である」という考え方があります。
5.DXの本質は“道具”ではなく“文化”
大学のDXを語るとき、私たちはつい「どんなシステムを導入するか」に目を向けがちです。
しかし、実際に必要なのは“仕組みの刷新”ではなく、“考え方の刷新”なのかもしれません。
紙を手放せないのは、便利だからではなく、“安心できるから”という面もあります。
それを一方的に否定するのではなく、現場の不安や業務の実態を丁寧にすくい取りながら、少しずつ文化を変えていくこと。
それが、大学事務における真のDXにつながる第一歩だと感じています。
小さな改善であっても、「これを電子化してみよう」「この手続きは紙なしで回してみよう」と職員一人ひとりが動き始めれば、
“紙文化”は少しずつ“デジタル文化”へと姿を変えていくはずです。
変化は上からではなく、現場から始まります。
その積み重ねこそが、大学の未来を静かに動かしていく力になるのではないでしょうか。
以上、お読みいただきありがとうございました!