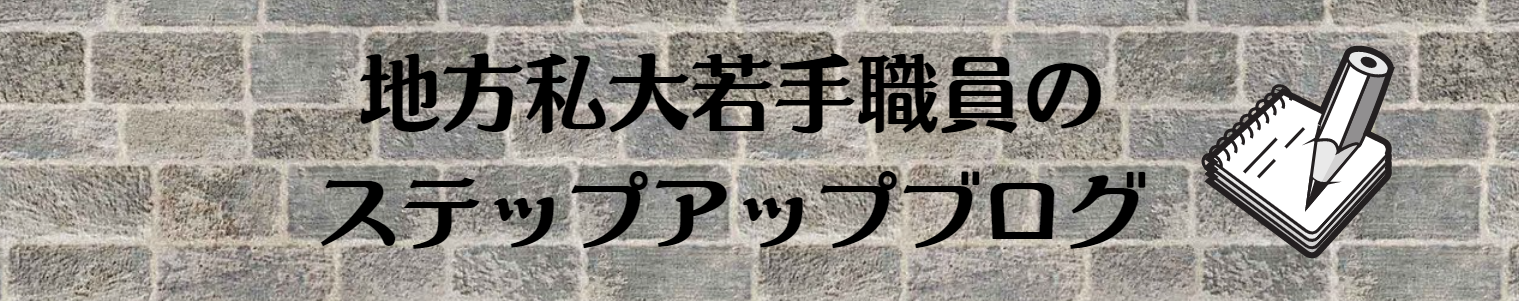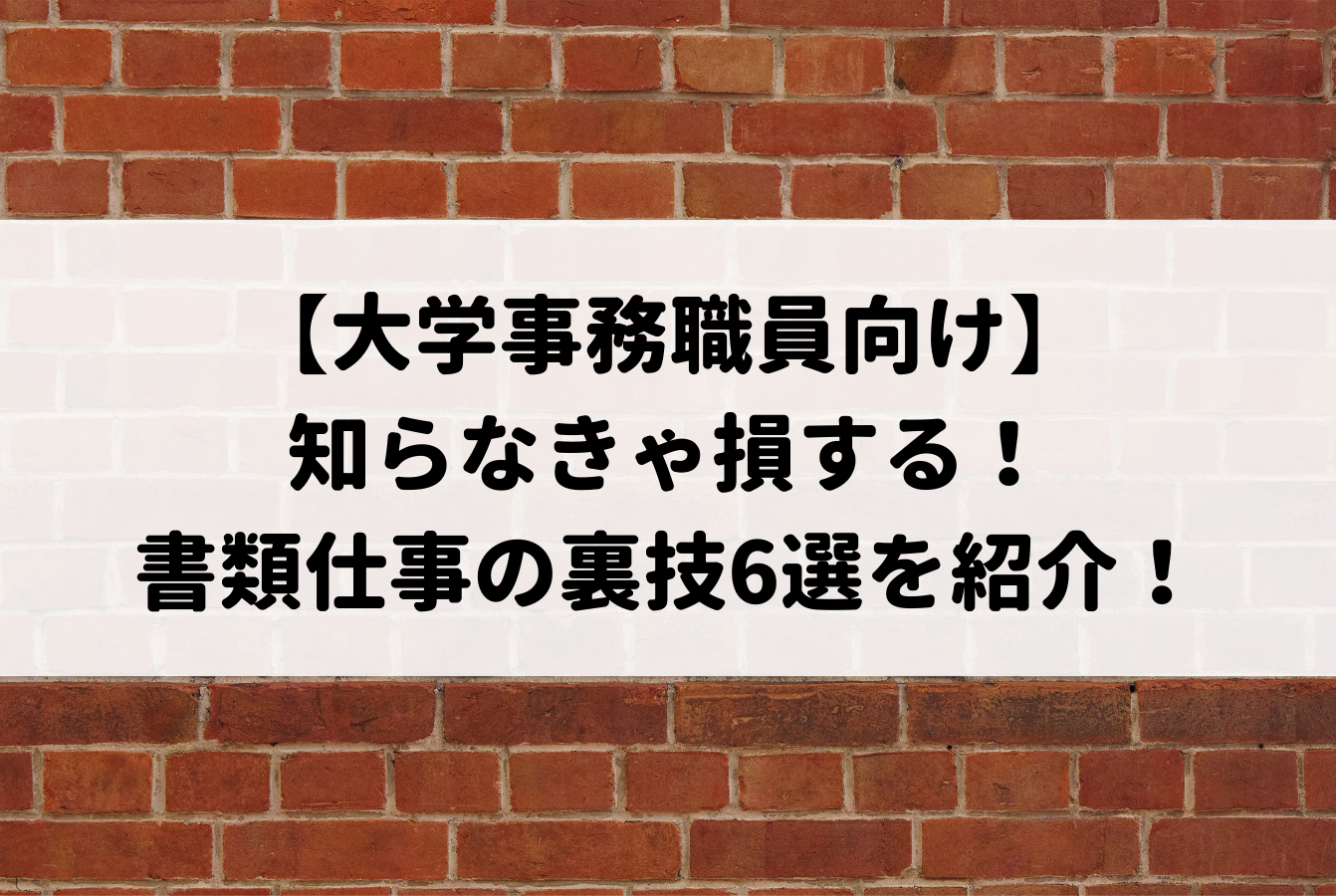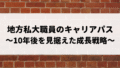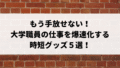こんにちは、ここあです。
大学職員として日々の業務に取り組む中で、「どうしてこんなに書類の処理に時間がかかるのだろう」「もっと効率よく進められないだろうか」と感じたことはありませんか?大学業務は多岐にわたりますが、その中でも書類作成や管理は避けて通れない重要な仕事です。しかも、学生対応や教員補助など、他業務と並行して進めなければならないため、いかに無駄を省き、正確に、そして迅速に処理できるかがカギになります。
本日は、日々の業務にすぐ活かせる「書類仕事の裏技」を6つご紹介します。ベテラン職員の方にも、新人の方にも、役立つ汎用的なテクニックを厳選しました。
【裏技①】テンプレートを“育てる”習慣をつける
大学では、類似した文書を何度も作成する機会が多くあります。たとえば学生への通知文や、教員宛の依頼文、各種証明書発行に伴う事務連絡など。こうした書類を都度ゼロから作るのではなく、業務のたびに少しずつテンプレートを“育てる”意識を持つことで、次回以降の作業効率は飛躍的に向上します。
ポイントは、「文面の調整履歴を残す」「バリエーションを増やしておく」「名前の付け方を工夫して検索しやすくする」こと。例えば、【学生通知_休講連絡_2025春】など、検索性の高い名称を付けると便利です。
【裏技②】Wordの「差し込み印刷」で個別対応を時短化
学生への個別文書を大量に作成する際は、Wordの「差し込み印刷」機能が非常に有効です。Excelに学生名・学籍番号・個別コメント等を一覧化しておけば、1クリックで個別対応文書を一括作成できます。
特に学費関連の通知、学内選考の結果通知などでは、テンプレートとExcelの組み合わせだけで“手書き対応”から脱却できます。周囲でまだ使っていない職員がいれば、ぜひ教えてあげてください。
【裏技③】メールテンプレートで「伝え漏れ」ゼロへ
学生や教職員へのメール対応では、文面の丁寧さと伝達内容の正確さが求められます。だからこそ、「メール定型文テンプレート」は非常に有効です。「件名の付け方」「本文構成」「問い合わせ先の記載」「締切日や注意事項の強調」など、業務ごとに基本形を準備しておけば、返信時間の短縮と伝達ミスの防止につながります。
OutlookやGmailでは「定型文登録」機能も使えます。部署内で共有フォルダを作って、誰でも使えるようにしておくとさらに効果的です。
【裏技④】チェックリストを「仕組み化」して抜け・漏れ防止
書類処理で最も避けたいのが、記載ミスや手続き漏れです。その防止策として有効なのが、チェックリストの活用。ただし、ただの紙のリストではなく、ExcelやGoogleスプレッドシートで“仕組み化”しておくことがポイントです。
たとえば、申請受付から処理完了までの各工程をリスト化し、進捗状況を「✔︎」「未着手」「対応中」などのステータスで記録できるようにすると、誰が見ても一目で状況が分かります。
【裏技⑤】時短の鍵は「並行処理」×「ゆるマニュアル」
新人職員からよく聞くのが「書類仕事に集中すると、他の業務が止まってしまう」という声。これは“属人化”のサインでもあります。そんなときは、マニュアルを「完璧なもの」にしようとせず、「とりあえず今日説明した内容をざっくりまとめる」くらいの“ゆるマニュアル”から始めてみてください。書類処理中に電話が鳴ったり、窓口対応が割り込んでも、他の職員がカバーできる状態を作るだけで、業務全体の流れは大きく改善します。
【裏技⑥】「過去文書データベース」を部署で共有しよう
過去に作成した書類が参考になることは多々あります。にもかかわらず、「あの書類、誰が持ってる?」「去年どうしてたっけ?」と探し回る時間は、意外と大きなロスになります。Google Driveや学内サーバーで「過去文書フォルダ」を整備し、年・業務別に分類しておくだけでも効果は絶大です。ポイントは「タイトルの付け方」と「検索性」。
裏技①と重複しますが、たとえば「2024_春_学外研修_申請様式」などと明確にしておけば、探す時間は格段に減ります。自分のためにも、後輩のためにも、引き継ぎの手間を最小限にできますね。
おわりに
書類仕事は大学職員にとって避けて通れない業務でありながら、その進め方によって大きな差が出る領域でもあります。今回ご紹介した6つの裏技は、特別なソフトや知識を必要としないものばかり。すぐに取り入れられるものばかりです。
“ちょっとした工夫”が、“大きな余裕”を生みます。職員一人ひとりがこうした工夫を重ねていくことで、チーム全体の業務効率も高まり、学生や教員に向き合う時間を確保しやすくなるでしょう。

あなたの書類仕事が、少しでもスムーズになりますように。
以上、お読みいただきありがとうございました!