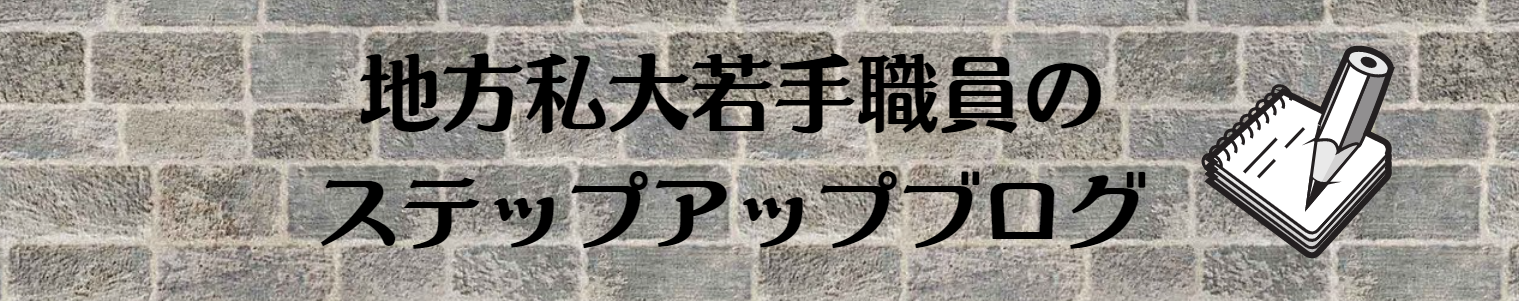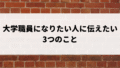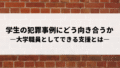こんにちは、ここあです。
未成年の飲酒は、いまやどの大学でも起こりうる現実的な課題です。
18歳で成人とされる現在、学生自身も周囲の大人も「もう大人だから」と飲酒を容認してしまうケースが後を絶ちません。特に、新歓コンパやゼミ旅行、学園祭後の打ち上げなど、“特別な場”では、雰囲気に流されて飲酒してしまうリスクが高まります。しかし、行き過ぎた未成年の飲酒は、体調不良や事故、SNSでの炎上、さらには大学の信頼問題に発展することもあります。
本記事では、実際に大学で起きた処分事例を交えながら、「なぜ未成年飲酒がなくならないのか」、そして「私たち事務職員にできることは何か」を整理します。
未成年飲酒の現状と大学の立場
日本の法律では、20歳未満の飲酒は禁止されています。
しかし、大学生の多くは18歳以上であるため、「大学生=飲酒OK」と誤解されがちです。
特に大学では、新入生歓迎会や課外活動、ゼミ旅行、学園祭の打ち上げなど、飲み会のきっかけが多く存在します。こうした場で未成年飲酒が発覚する事例は後を絶ちません。
大学としては、飲酒に関する明確なガイドラインを設け、学生への継続的な周知啓発を行うとともに、違反があった場合には学則に基づき厳正に処分を下す必要があります。
安全配慮義務や社会的責任を果たすという観点からも、未成年飲酒への対応は大学運営上、極めて重要なテーマです。
報道にみる未成年飲酒の処分事例
それでは、実際の未成年飲酒の事例を見てみましょう。なお、具体的な大学名や学年・日付は、報道記事を参考に一般化しています。
事例①:合宿先での急性アルコール中毒死亡
- 未成年の 1 年生男子が合宿先で大量飲酒し死亡。
- 大学は当該サークルの飲酒を伴う行事を全面禁止。
- 関与学生には停学・厳重注意などの懲戒処分。
事例②:部室での飲酒による急性アルコール中毒死
- 19 歳女子学生が部室で飲酒後に意識を失い搬送先で死亡。
- これを受け、学内での飲酒を原則禁止へ。
- 部の活動停止と再発防止研修を義務付け。
事例③:新歓コンパでの死亡事故と懲戒
- 18 歳学生が急性アルコール中毒で死亡。
- 飲酒を強要した上級生 1 名が退学、複数名が無期停学。
- 管理責任を問われた教職員も訓告・辞任。
これらの事例が示すのは、未成年飲酒が「学生個人の問題」にとどまらず、サークルや教職員、大学全体のガバナンスが問われる事態へ発展し得るという事実です。
なぜ、未成年飲酒はなくならないのか?
未成年飲酒が繰り返される背景には、複数の構造的な要因があります。
まず、成人年齢の引き下げにより18歳で契約や選挙が可能となったことで、「もう大人だから飲酒もOK」と誤認されやすくなっています。加えて、飲食店でIDチェックが徹底されていない実情もあり、飲酒のハードルは以前より下がっています。
また、一部の大学文化には、「飲んで当たり前」「飲めないとノリが悪い」といった雰囲気が根強く残っており、飲み会でお酒を断りにくい空気や先輩からの無言の圧力が、未成年者の飲酒を後押しする環境を生んでいます。
さらに、「大学生なら多少は仕方ない」といった教職員や保護者による“暗黙の容認”が、適切な指導の機会を逃す要因にもなっています。
こうした背景が重なり、未成年飲酒は「どこでも起こりうる問題」となっているのです。
事務職員としてできる3つの対策
学生への情報提供と啓発
新入生オリエンテーションなど、早い段階から「20歳未満の飲酒は違法である」という事実を明確に伝えることが重要です。学内ポータル、掲示板、SNSなどを活用し、定期的に注意喚起を行いましょう。急性アルコール中毒のリスクや過去の事例を具体的に共有することで、学生の危機意識を高めることができます。
教職員間での情報共有と体制整備
過去の処分事例を教員と共有し、問題が発生した際の対応フローを明文化することで、誰もが迷わず動ける体制をつくれます。事務職員が教員や学生課と連携しやすいように橋渡しする役割を担うことも、円滑な対応につながります。
課外活動への予防的な関与
サークル活動や合宿、懇親会といった“飲酒が起こりやすい場面”には、あらかじめ目を配ることが効果的です。活動申請時に未成年飲酒禁止の誓約書の提出を義務づけたり、飲酒が想定される行事は事前届出制にするなどの工夫が抑止力となります。さらに、行事後に簡単な活動報告を求めることも、学生の意識づけに有効です。
このように、事務職員が日常の接点で「声をかける」「予防線を張る」「体制を整える」といったアプローチを積み重ねていくことが、未成年飲酒の抑制につながります。
処分後の“支援”も忘れずに
処分を下すだけでは、根本的な再発防止にはつながりません。大切なのは、処分後のフォローアップです。本人との面談や振り返りを通じて、「なぜ飲酒に至ったのか」「これからどうするべきか」を共に考える機会を持つことが重要です。反省と再出発の道筋を示すことで、学生の成長へとつながります。
特に、履修相談や就職支援など学生の生活に寄り添う場面が多い事務職員だからこそ、処分後の立て直しを支える存在になれるのです。
おわりに
本日は、大学生の未成年飲酒にどう向き合うかについてお話ししました。
未成年飲酒は、決して一部の大学や特定の学生に限った問題ではありません。私たち事務職員は、これを「いつでも、どこでも起こりうること」として日常的に備えておく必要があります。
処分するだけでなく、予防し、支援すること。
学生の過ちに向き合い、次のステップを一緒に考えること。
それこそが、学生と大学を支える事務職員の本質的な役割ではないでしょうか。
以上、お読みいただきありがとうございました!