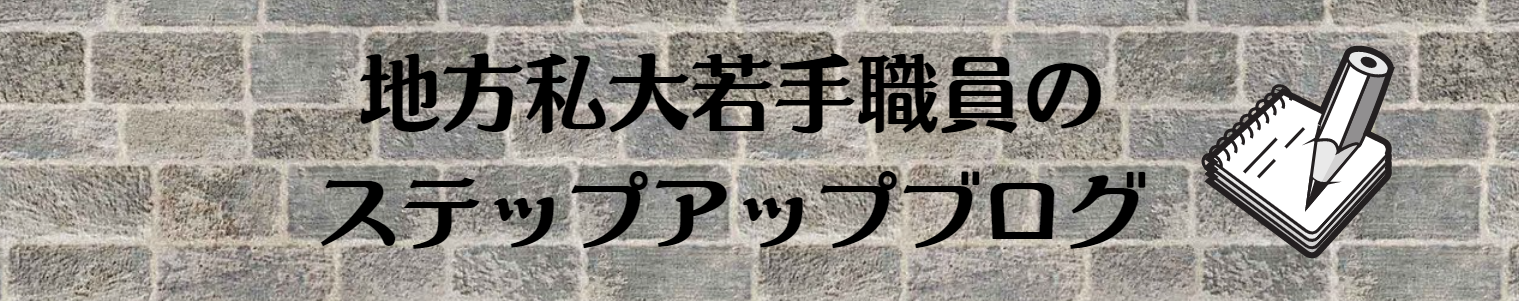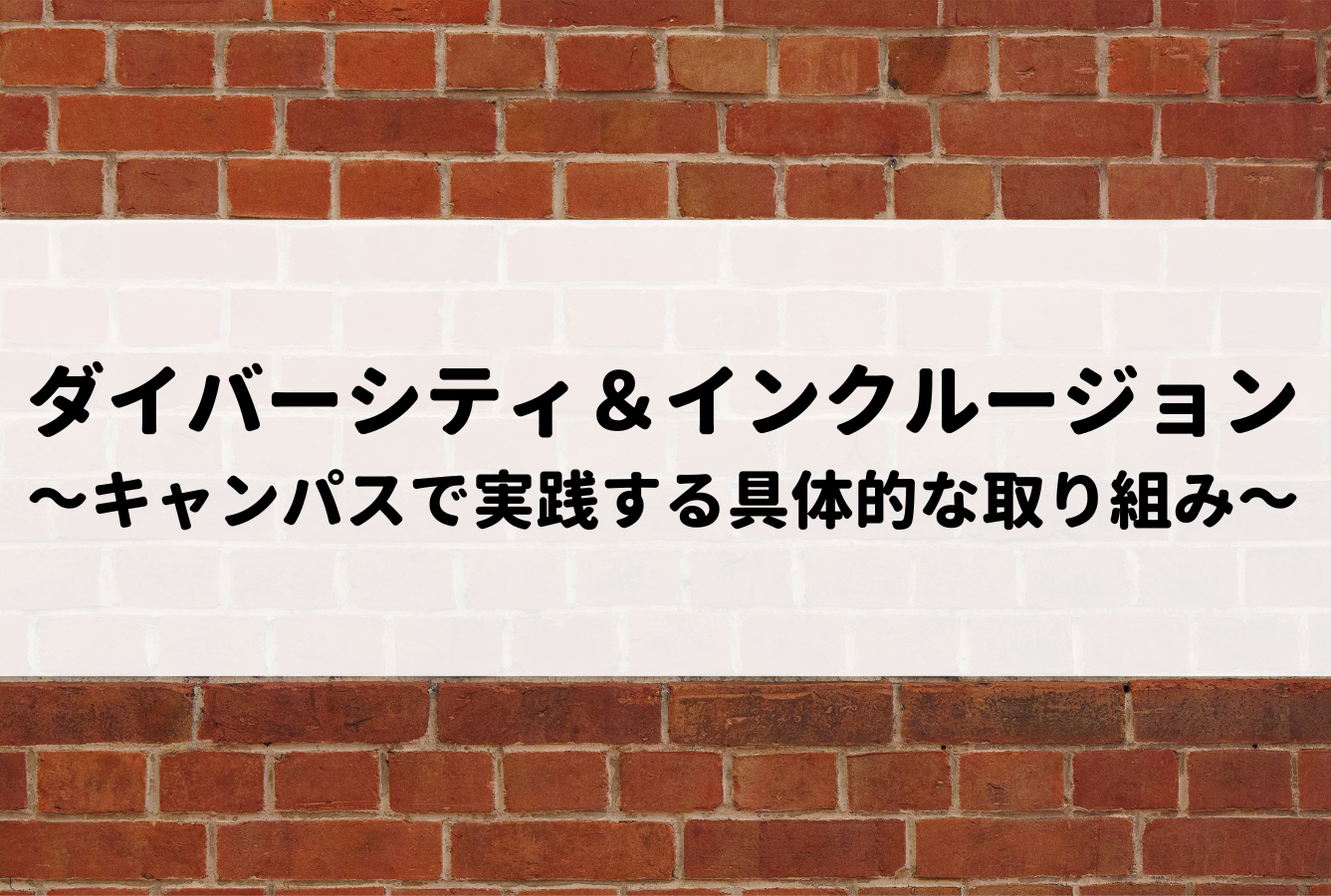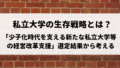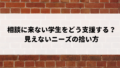こんにちは、ここあです。
「ダイバーシティ」と「インクルージョン」について、近年とても重要視されているテーマであり、言葉自体は知っているけれど、実際にどういう意味なのか分からないという方も多いのではないでしょうか。本日はダイバーシティ&インクルージョンの概要を説明するとともに、実際の大学における取り組みをみていきましょう。
ダイバーシティ(多様性)とインクルージョン(包括性)とは
ダイバーシティ(多様性)とは、簡単に言うと「違いを大切にすること」です。人それぞれ、性別や年齢、文化、宗教、障がい、性的指向など、異なる背景を持っています。それを「当たり前」として受け入れ、互いの個性を尊重することがダイバーシティの考え方です。
一方、インクルージョン(包括性)は、その「違い」を認めたうえで、すべての人が平等に参加できる環境を作ること。単に「多様な人がいる」だけでなく、誰もが自分らしく活躍できる場を提供することが大切です。つまり、インクルージョンは「受け入れる」こと以上に、「一緒に作り上げる」ことが求められます。
ダイバーシティ(多様性):違いを認め、多様な人々の存在を尊重すること。
インクルージョン(包括性):違いを尊重しつつ、誰もが平等に活躍できる環境を整えること。
この2つが組み合わさることで、より創造的で、すべての人が自分らしく生きられる社会や組織が実現できます。
私立大学におけるD&Iの特徴
さて、ここからは私立大学におけるD&I(Diversity & Inclusion)についてお話しします。私立大学は、地域や文化の多様性が色濃く反映される場であり、学生一人ひとりの違いを尊重し、支援することが特に重要です。
たとえば、私立大学には国際的な学生、編入生、社会人学生など、さまざまなバックグラウンドを持つ学生が在籍しています。そのため、D&Iの考え方を取り入れた取り組みが不可欠なのです。
私立大学でのD&I推進の具体例
D&Iの推進は、大学の環境や学生の特性に応じて多様な形で展開されています。特に私立大学は、国公立大学に比べて柔軟な制度設計が可能なため、独自の取り組みを積極的に進めています。ここでは、具体的な事例を紹介します。
学生の多様性を尊重した支援体制
私立大学では、学生の背景やニーズに応じた支援を行っています。
個別対応のカウンセリングとメンタルサポート
留学生や障がいのある学生、LGBTQ+の学生など、異なるバックグラウンドを持つ学生が安心して学べるよう、専属のカウンセラーを配置する大学が増えています。例えば、ある私立大学では、学生一人ひとりの状況に合わせたカウンセリングを提供し、学業・生活・キャリアの側面から包括的なサポートが行われています。
経済的支援の多様化
学費の負担を軽減するため、奨学金制度の充実も進んでいます。高等教育の修学支援制度だけでなく、地域貢献活動に参加した学生に対する奨学金プログラムも実施することにより、経済的な事情を理由に進学を諦める学生を減らす取り組みが進められています。
多文化共生のためのプログラム
多文化共生のための取り組みは、単なる留学生支援にとどまらず、異文化理解を深める教育や体験型プログラムとして展開されています。
バディ制度の導入
多くの私立大学では、留学生と日本人学生をペアにして学習や生活のサポートを行う「バディ制度」を導入しています。例えば、関東のある大学では、外国人留学生と日本人学生が定期的に交流し、お互いの文化を学ぶ機会を提供。これにより、留学生の孤立を防ぎ、日本人学生にも異文化理解の機会が生まれています。
多文化交流イベントの開催
異文化を学ぶ機会として、地域住民や企業と連携したイベントも活発に行われています。
東京の私立大学では、「多文化フェスティバル」を毎年開催し、世界各国の料理、音楽、ダンスなどを通じて異文化交流を推進。これにより、キャンパス内外で多様性を尊重する意識が高まっています。
学生一人ひとりの学びのスタイルを尊重
私立大学の強みの一つは、学生のライフスタイルやキャリアプランに応じた柔軟な学びの提供です。
オンライン学習の充実
地方や海外に住む学生、仕事をしながら学ぶ社会人学生向けに、オンライン講義やハイブリッド授業を拡充している大学が増えています。
例えば、とある私立大学では、地方在住の学生が通学せずに学べる「完全オンラインコース」を提供し、遠隔地からの受講を可能にしています。
夜間・週末講義の開設
社会人学生や子育て中の学生向けに、夜間や週末に開講する講義を増やす動きもあります。
例えば、社会人が学びやすい「リカレント教育(学び直し)プログラム」を整備し、キャリアアップや転職を目指す学生を支援。これにより、ライフステージの変化に合わせた学びの選択肢が広がっています。
地域社会との連携による包摂的な学びの場づくり
大学のD&Iの取り組みは、学内にとどまらず、地域社会との連携を通じて広がっています。
地域住民との交流プログラム
地方の私立大学では、地域住民と学生が協力して学ぶ機会を積極的に提供しています。
例えば、高齢者と学生が共同で地域の歴史を調査し、デジタルアーカイブを作成するプロジェクトを実施。世代を超えた学び合いの場が生まれ、学生は地域への理解を深めるとともに、社会貢献の意識を高めています。
地元企業やNPOとの協働プログラム
企業やNPOと連携し、地域の課題解決に取り組むプロジェクトも増えています。
例えば、地元の観光業と協力し、外国人観光客向けの多言語案内システムを開発することより、学生は実践的なスキルを身につけると同時に、D&Iの理念を社会に還元する機会を得ています。
おわりに
本日は、ダイバーシティ&インクルージョンにおけるキャンパスで実践する具体的な取り組みについてお話ししました。
D&Iは私たち一人ひとりが自分らしく生き、活躍するために欠かせない考え方です。私立大学でも、学生がより良い環境で学べるよう、さまざまな取り組みが進んでいます。こうした動きが広がることで、誰もが自分らしく輝ける社会が実現していくのではないでしょうか。

私たちも、日々の生活の中でD&Iを意識し、小さな行動から変えていけるといいですね!
以上、お読みいただきありがとうございました!