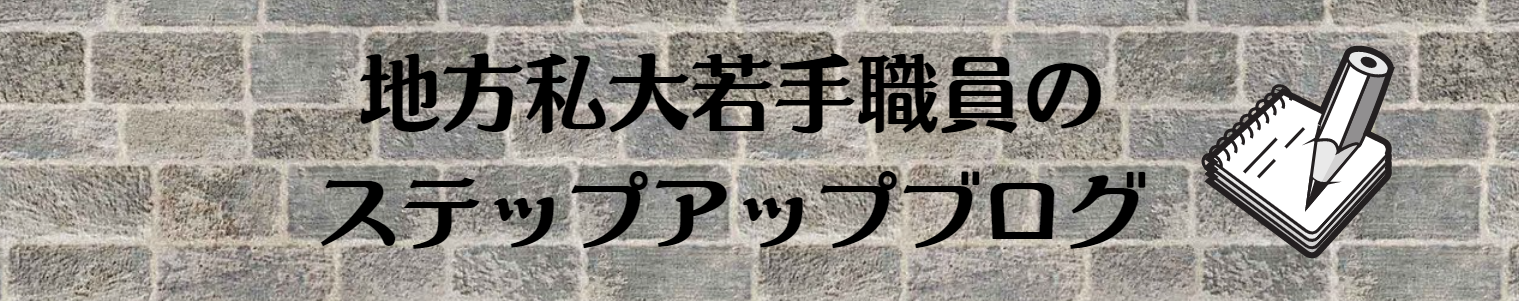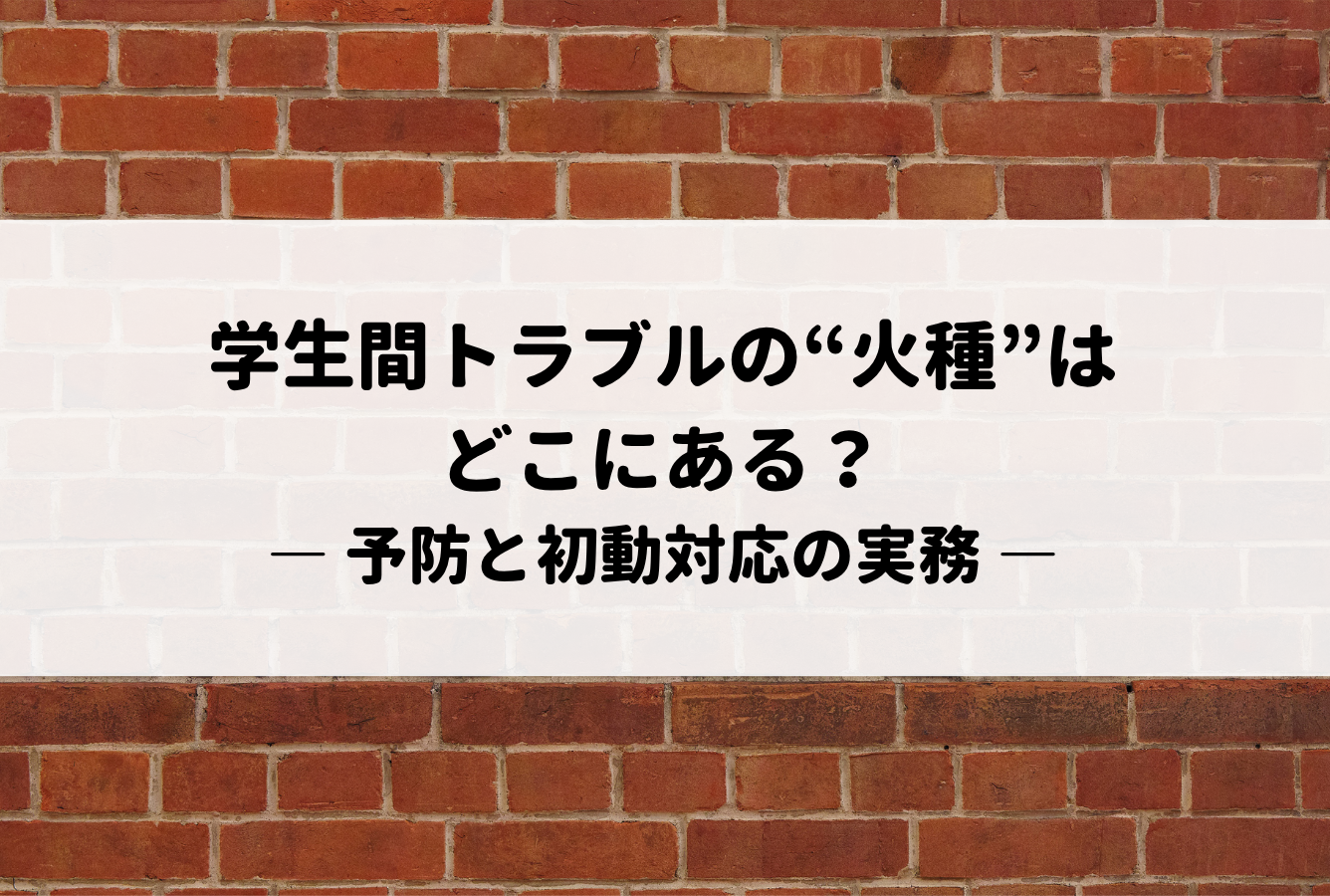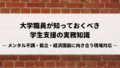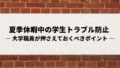「ちょっとした行き違いが、大きなトラブルに発展していた――」
そんな場面に心当たりのある大学職員の方も多いのではないでしょうか。
近年、学生間のトラブルはますます多様化・複雑化しています。
特にSNSの普及により、目に見えないところで不信感が広がったり、悪意のない一言が深刻な関係悪化を引き起こしたりするケースが少なくありません。
今回は、学生間トラブルの“火種”を未然に防ぎ、万が一発生した場合の初動対応について、大学職員として押さえておきたい実務ポイントをまとめます。
「ちょっとしたこと」が引き金に
火種になりやすい場面・背景
大学内でよく見られる学生間トラブルは、以下のようなものです。
- グループワークでの温度差・責任の押しつけ合い
- 部活やサークル内での上下関係・排除行為
- SNSでの発言や裏アカの拡散
- 文化的背景や価値観の違いによる摩擦
- 同居やルームシェアでの生活習慣の違い
特に近年は、「相手に悪意があったかどうか」よりも、「自分が傷ついたと感じたかどうか」が問題化する要因になっています。
こうした背景には、コロナ禍を経て対人スキルに不安を抱える学生の増加や、自己肯定感の低さ、対話経験の不足といった課題が見え隠れします。
火種を大きくしないために ―予防の視点と環境づくり―
学生間トラブルを防ぐには、“学生をよく知る”ことが第一歩です。以下のような予防策が、トラブルの芽を摘むことにつながります。
1. 日常的な声かけ・雑談の力
学生が不安や悩みを抱えたとき、「この人になら話せそう」と思える関係性があるかどうかが、大きな分かれ道になります。そのためには、日常的な声かけや雑談を通じて、職員と学生のあいだに“安心して話せる空気”を作っておくことが大切です。
ちょっとした立ち話や提出物のやりとりのなかで、「最近どう?」「グループ活動は順調?」といったライトな会話を交わすだけでも、学生の表情やトーンから変化に気づくきっかけになります。

トラブルの予防は、制度よりも信頼感の積み重ねから始まります!
2. ハラスメント・人権に関する研修の実施
学生が集団で行動する部活動やサークル、ゼミなどのコミュニティでは、力関係の偏りや古い慣習が、知らず知らずのうちにトラブルの温床になっていることがあります。
「自分がされたことを後輩にもするのが当然」
「空気を読めない人が悪い」
こうした価値観が残る場では、無自覚なハラスメントや排除行動が起こりやすくなります。
これを防ぐためには、学生自身に「何がハラスメントになるのか」「どんな言動が問題とされるのか」を定期的に伝えていくことが必要です。
具体的には、
- サークル代表者向けの年1回の人権研修
- ゼミや授業内での短時間の啓発スライド
- ハラスメント対応フローの共有
など、一斉指導+継続的周知の仕組みづくりが効果的です。
3. 情報提供と通報窓口の周知
「困っていても、どこに相談すればいいかわからない」
この状態こそが、トラブルを深刻化させる最大の要因のひとつです。学生が相談の第一歩を踏み出せるようにするには、窓口の存在を“何度でも・目につくかたちで”伝えることが大切です。
「誰が」「どこで」「どんなことを相談できるか」が明確になっていれば、学生はトラブルの早期段階で声を上げやすくなります。
もし起きてしまったら ― 初動対応の基本と実務ポイント ―
どれだけ注意していても、トラブルが発生することはあります。問題が発覚したとき、職員として押さえておきたいポイントは以下の通りです。
1. 事実の確認は「中立・丁寧」に
トラブルの相談を受けたとき、まず意識したいのは「どちらかの肩を持たない」中立的な姿勢です。
双方の言い分を冷静に丁寧に聞き取りながら、「主観」ではなく「事実」を確認することが重要です。
- 何が、いつ、どこで、どのように起きたのか
- それに対して、どう感じ、どう対応したのか
最初から「被害者・加害者」という枠組みにあてはめてしまうと、かえって関係がこじれることもあります。まずは“関係性のすれ違い”として捉える視点を持つことが、冷静な対話への第一歩です。
2. 必ず記録を残す
トラブル対応では、記録が極めて重要です。口頭だけでやりとりを終えてしまうと、後から「言った・言わない」や「事実誤認」が起こる可能性があります。
- ヒアリングの日時・場所・参加者
- 発言の要旨(なるべく事実ベースで)
- 今後の対応方針・確認事項
などを、職員個人だけでなく部署内でも共有できるように記録を残しましょう。必要であれば、学生にも確認・了承を取っておくと安心です。
3. 一人で抱えない、連携する
複雑な事案になるほど、「自分だけで対応してよいのか?」と判断に迷うことも増えます。
そんなときは、遠慮なく他部署・専門家と連携することが鉄則です。
- 学生相談室(心理的支援)
- 顧問教員や学科長(教育上の視点)
- ハラスメント相談員・人権委員会
- 法務・総務部門(法的な観点)
特に、対応方針に温度差が出やすい場面では、複数名でケース共有・判断を行うことで、対応の一貫性と公平性が保てます。
トラブルを「教育機会」とするために
トラブルは、学生本人にとっても職員にとってもストレスの大きい出来事です。
しかし同時に、他者との違いや対話の大切さを学ぶきっかけにもなり得ます。
- 関係者の感情に配慮しながら、行動面での反省・再発防止を促す
- サークル・ゼミ全体に「組織としてのルールと対話の大切さ」を伝える
- 定期的に「トラブル対応事例」を共有し、学内の知見を蓄積する
など、初動対応後には、上記のような視点を大切にするとよいでしょう。
おわりに
学生間のトラブルは、決して珍しいことではありません。似た環境で生活し、価値観の異なる学生たちがともに学ぶ大学では、すれ違いや誤解が生じるのは自然なことです。だからこそ、私たち大学職員がその“火種”に早めに気づき、必要に応じて穏やかに介入する力が求められます。
職員として日々の中でできることは、想像以上に多くあります。窓口でのちょっとした会話や、学生の表情の変化に気づく観察力。何かあったときに「話してみようかな」と思ってもらえる信頼関係。そうした積み重ねが、トラブルの予防や早期発見につながります。
私たち事務職員の関わりは、直接的な指導ではなくても、学生の安心や成長に確かに寄与するものです。困っている学生のそばに、気づき、声をかけ、話を聴ける人がいること。それだけでも、大学という場所が少し優しく、強くなっていくのではないでしょうか。