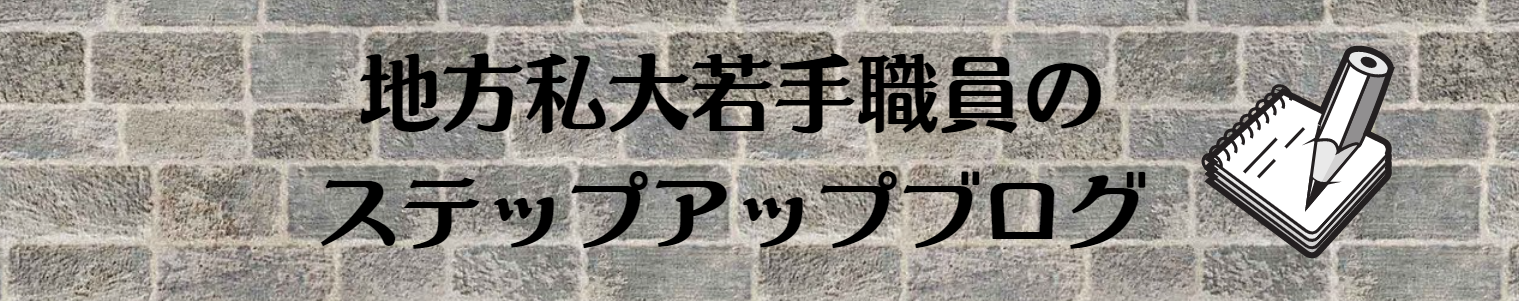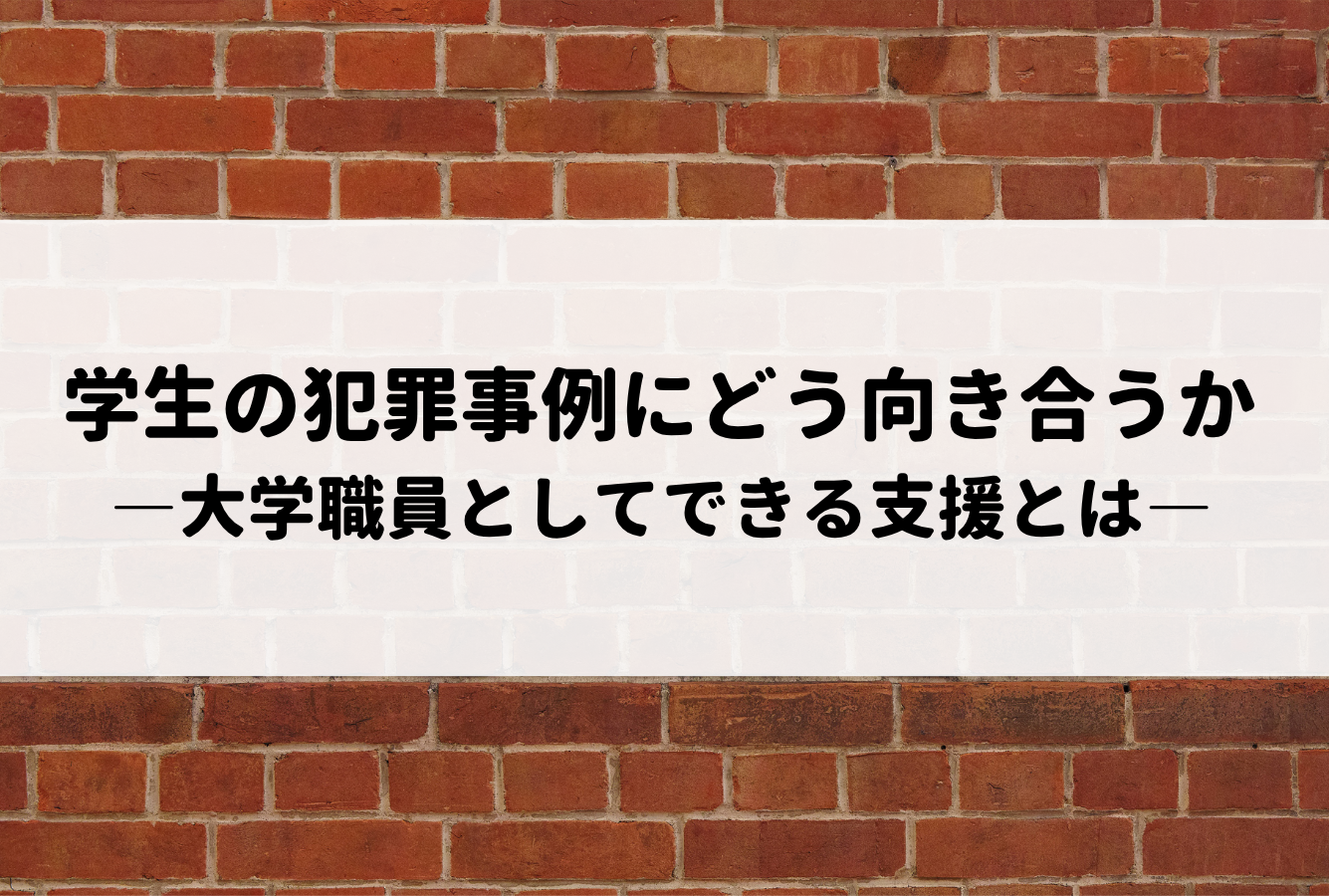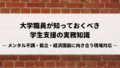「まさか、うちの学生が…」
そう思わずにはいられないようなニュースに、大学職員として衝撃を受けた経験がある方もいるのではないでしょうか。盗撮や痴漢、薬物使用、特殊詐欺の“受け子”としての関与など、大学生による犯罪行為やその巻き込まれ事例は、もはや特別な出来事ではなくなっています。
もちろん、犯罪は個人の責任に帰するものであり、大学としては厳正に対処せざるを得ません。しかし同時に、なぜ学生がそのような行為に至ったのか、どんな背景があったのかを考えることも、私たち大学職員に求められる姿勢ではないでしょうか。
本記事では、近年見られる学生の犯罪事例をもとに、その背景や大学としての対応、そして事務職員としてできる支援について考えていきます。
学生の犯罪事例――現実に起きていること
ケース1:特殊詐欺の“受け子”として逮捕
ある大学生が、SNSを通じて「高収入バイト」に応募し、指定された口座から現金を引き出して運搬した結果、特殊詐欺の共犯として逮捕されました。本人は「仕事内容の詳細を知らなかった」と供述していたものの、結果として高齢者をだます詐欺グループの一員として処罰されました。
ケース2:コンビニでの万引き
アルバイトの帰りにコンビニで食品を万引きし、警察に通報された大学生。事情聴取では「お金がなかった」「魔が差した」と話していました。大学では停学処分となり、その後の就職活動にも大きな影響を及ぼしました。
ケース3:盗撮で現行犯逮捕
大学の構内トイレで盗撮をしていた学生が、学生によって通報され現行犯逮捕。調査の結果、スマートフォンには複数の盗撮画像が保存されており、大学は退学処分を決定。事件はマスコミにも報道され、大学の広報対応にも大きな影響を与えました。
背景にある「個別の事情」と「環境要因」
こうした事件の根底には、学生個人の「判断の甘さ」や「軽率な行動」があることは否定できません。しかし、それだけで済ませてしまうと、同じような事例を未然に防ぐ機会を逃してしまいます。
経済的な困窮や孤立
コロナ禍以降、家庭の収入減やアルバイトの減少により、経済的に追い詰められる学生が増えました。親や大学に頼れず、「すぐにお金が必要」となる中で、安易に怪しいアルバイトに手を出してしまうケースもあります。
情報リテラシーの低さ
SNSやネット掲示板で簡単に「バイト情報」や「やり方」が手に入る現代では、裏の危険性を認識せず、犯罪に関与してしまう学生も少なくありません。特に初犯の場合、「これは犯罪なのか分からなかった」という言い訳も、完全に嘘とは言い切れない現実があります。
メンタルヘルスの問題
うつ状態やストレス、自己肯定感の低下など、精神的な不安定さが行動の抑制を弱めることもあります。衝動的な行動や、現実逃避的な動きとして、犯罪に手を染めてしまうこともあるのです。
大学の対応と課題
処分対応の現実
学生が警察沙汰を起こした場合、大学側は調査委員会等の調査機関を設置し、懲戒処分を検討します。停学・退学処分の基準は各大学で異なりますが、社会的影響や再発リスクを考慮して厳正な対応が求められます。
一方で、学生にとって大学は「更生の場」でもあります。事件の背景や更生の意志が見られる場合には、指導を通じて社会復帰を支援する道を残すべきという声も根強くあります。
被害者や関係者への配慮
犯罪によって被害者がいる場合、大学としては被害者への対応も重要です。謝罪や再発防止策の提示、時には外部機関との連携も必要です。関係者のケアも含めた「総合対応」は、大学の信頼を守るうえでも不可欠です。
事務職員としてできる支援
私たち大学職員は、警察のように捜査や逮捕ができる立場ではありません。しかし、日常的な学生対応の中で「違和感」に気づいたり、必要な支援につなげたりすることはできます。
小さなサインを見逃さない
「なんとなく元気がない」「最近よく遅れてくる」「提出物が急に出せなくなった」――学生からのこうした小さな変化は、事務窓口やメール・電話応対などでもふと垣間見えることがあります。
事務職員は、教員ほど密に接するわけではありませんが、逆に“適度な距離感”があるからこそ、学生が気軽に本音を漏らせる存在にもなり得ます。
たとえば、「最近忙しそうだね」と軽く声をかけることで、学生が思わず悩みを話し始めることもあります。深刻な問題が潜んでいることもあるので、違和感を覚えたときにはメモに残しておく、関係部署と情報を共有しておくなど、小さな備えが大きなリスク予防になります。
対応の第一歩は「気づくこと」。私たちの仕事の合間に見える“変化の兆し”を見逃さないことが、支援の入口になります。
窓口の“壁”を下げる工夫
学生課や教務課の窓口は、私たちにとっては日常の職場ですが、学生にとっては“少し入りにくい場所”です。とくに悩みを抱えた学生ほど、用件なしで立ち寄ることにためらいを感じやすく、「こんなこと相談していいのかな」「怒られそう」と誤解されがちです。
だからこそ、私たちができるのは「ここに来ていいんだ」と思わせる空気をつくること。たとえば、
- 案内掲示やチラシに、柔らかい表現やイラストを使う
- 「何でも相談OK」のポスターを掲示する
- 学生生活で起こりがちな困りごとをQ&A形式で紹介する
- Webフォームや匿名での相談チャットなどの導線を整備する
といった工夫によって、「行ってみようかな」と思えるきっかけを生み出すことができます。支援の入り口が閉じていては、支援そのものが届きません。
窓口を“相談を避けられない場所”ではなく、“相談してもいい場所”へ変えていくことが、事務職員の大切な役割です。
啓発や注意喚起の仕掛け人になる
事務職員は学生と日常的に接する機会が多く、掲示物や学内ポータル、ガイダンス資料など、情報発信のハブとしての役割を担うことができます。この立場を生かして、「危ないバイト情報に注意」「万引きも犯罪です」などの啓発情報を発信する役割を積極的に担っていくことが大切です。
たとえば、
- 危険なバイト募集事例を紹介するミニ掲示コーナー
- 詐欺や薬物に関する注意喚起ポスターの掲示
- 新入生向けオリエンテーション資料に「犯罪と責任」についての一言コラムを掲載
など、ちょっとした工夫で「気づきの機会」を増やすことができます。
また、単に「ダメ、絶対」と伝えるだけでなく、「なぜいけないのか」「どうすれば避けられるか」といった具体的な視点を盛り込むことで、学生の理解度や納得感を高めることができます。
おわりに
大学生の犯罪事例は、学生本人の人生を大きく変えるだけでなく、大学全体の信頼性や安全性にも関わる重大な問題です。だからこそ、単なる処分や対処で終わらせるのではなく、背景を見つめ、支援と再発防止に向けた取組みが求められます。
私たち大学職員は、教員のように直接授業で学生と接する機会は少ないかもしれません。しかし、窓口や事務対応のなかで、学生の「小さな変化」に気づき、声をかけ、支援につなげることができます。
学生の過ちを責めるだけでなく、どうすればその芽を早く見つけ、摘まずに育て直せるか――。そうした視点を持ちながら、私たちの業務のあり方も少しずつ見直していきたいものです。